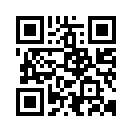2006年05月07日
市内・歴史保存地区

市内平清水(ひらそうず)の龍源寺(りゅうげんじ)にある太子塔です。聖徳太子の像が祀られており、臼杵市のシンボル的な建物です。1858年(安政5年)に10年をかけて立てられたものだそうです。江戸時代末期の名工臼杵出身の高橋団内の作ということです。

臼杵市内の中心的な本町商店街。以前はアーケードがありましたが、老朽化したので撤去されました。明るくなって、良かったと思います。それにつれて、この先には、観光案内所などがあります。

これを左手に入ると歴史保存地区がはじまります。二王座歴史の道として整備されています。細い道が何本も山手に伸びており、歩いていくと目の前にピンクのつつじが飛び込んできました。

臼杵はお寺の多いところで数十はあるとおもいます。香林寺の塀に枝垂桜の木が葉陰を落としていました。満開のときに来たかったですねえ。

お寺と武家屋敷が連なっています。真ん中あたりに臼杵城跡にできた大手門が見えます。歩いて10分ほどでしょうか。

このあたりは上級武士の屋敷跡だそうです。春日の局がこのあたりに住んでいたという話もあります。

上の写真から振り向いて右手に下るとすぐ明石原人の発見者の直良信夫博士(なおら・のぶお)の生誕の地があります。直良博士についてはまたいつか書きます。

直良博士の家の前を下ってきたところです。本当は三重塔から逆にしたから上へと歩いたのです。子供のころこの道は数十回とは言わず歩いていたので、路地一つ一つが懐かしさで一杯です。つい入り込んでしまいます。

映画「なごり雪」の舞台になって、観光客もふえました。こういう瀟洒なお店がたくさんできました。
今度、大林監督の「二十二歳の別れ」の撮影が始まると言う話で持ちきりです。尾道三部作のように臼杵三部作ができるのだと思います。
Posted by Sorin at 12:42│Comments(16)
│臼杵
この記事へのコメント
良い町並みですね。3番目とか、6番目の写真、向かい合った家の片方に石垣があって、片方がないのは何か意味があるんでしょうか?
Posted by ゲスト at 2006年05月07日 19:02
>Inaさん、こんばんは。
それはですね。土地が傾いているのです。たとえば3番目の写真で言うと左側から右へ傾いているので、家を建てるためには左側は石垣を組んで水平をとる。6番目は逆ですね。
ですから、この先に行けば、石垣のない家は、石垣を持ち、石垣のあった家は石垣が有りません。
それはですね。土地が傾いているのです。たとえば3番目の写真で言うと左側から右へ傾いているので、家を建てるためには左側は石垣を組んで水平をとる。6番目は逆ですね。
ですから、この先に行けば、石垣のない家は、石垣を持ち、石垣のあった家は石垣が有りません。
Posted by Kiyo at 2006年05月07日 19:23
とんでもない、堂々たる城下町なのですね。いつか訪れてみたいものです。
Posted by jijii at 2006年05月07日 19:28
Kiyoさん、ご返事ありがとうございました。地形のせいなんですね。高さがあまりに高いので、身分の差かと思いました。今までずっと「ニッポン人が好きな偉人ベスト100人」を見てましたが、織田信長が一位で、日本人は昔から変わらず、織田信長が好きなんですね。
Posted by ゲスト at 2006年05月07日 22:17
思い浮かべました.
Posted by Ritchie at 2006年05月08日 05:30
>jijiiさん、こんばんは。
石仏が一番有名でしょうね。ちょっと町外れにあります。車で30分くらい。城下町と言ってもたかだか5万石ですから知れています。武士もたしか200〜300人位ではなかったかと。下級武士は食べるのがやっとだったと思います。金沢の武家屋敷に比べたら。いや比べる必要はありませんね。ぜひ来てください。
石仏が一番有名でしょうね。ちょっと町外れにあります。車で30分くらい。城下町と言ってもたかだか5万石ですから知れています。武士もたしか200〜300人位ではなかったかと。下級武士は食べるのがやっとだったと思います。金沢の武家屋敷に比べたら。いや比べる必要はありませんね。ぜひ来てください。
Posted by Kiyo at 2006年05月08日 21:27
こういう風に残っているところは日本中探してもそんなにないのでは?
Posted by kuronekokotoshan at 2006年05月08日 21:28
>Inaさん、こんばんは。
そうですね。確かに身分の差もありますよ。上に行くほど身分の高い人の家が多いはずですから。でもお寺も多いので、石垣だけではわかりません。でも上から6枚目は確かに右側は高位の武家の家のはず。門まで30段くらいの幅の広い石段があります。下から2枚目は左側はお寺の墓地、右はがけです。とにかく高低差がすごいです。
そうですね。確かに身分の差もありますよ。上に行くほど身分の高い人の家が多いはずですから。でもお寺も多いので、石垣だけではわかりません。でも上から6枚目は確かに右側は高位の武家の家のはず。門まで30段くらいの幅の広い石段があります。下から2枚目は左側はお寺の墓地、右はがけです。とにかく高低差がすごいです。
Posted by Kiyo at 2006年05月08日 21:48
>Ritchieさん、こんばんは。
法隆寺より少し小さいとは思いますが、九州に2つしかない江戸時代の木造三重塔だそうです。あと1つがどうしても気になります。どこかなあ。
法隆寺より少し小さいとは思いますが、九州に2つしかない江戸時代の木造三重塔だそうです。あと1つがどうしても気になります。どこかなあ。
Posted by Kiyo at 2006年05月08日 22:19
>ことしゃん、こんばんは。
いえいえ、結構あちこちにあると思いますよ。大分だけでも、佐伯、杵築、日田など。大分も。
でも大林監督も臼杵がかなり気に入ったみたいで、次回作にも臼杵が写るそうです。「二十ニ才の別れ」だとか。
いえいえ、結構あちこちにあると思いますよ。大分だけでも、佐伯、杵築、日田など。大分も。
でも大林監督も臼杵がかなり気に入ったみたいで、次回作にも臼杵が写るそうです。「二十ニ才の別れ」だとか。
Posted by Kiyo at 2006年05月08日 22:23
素敵な街並みですね。
普段そんなに気にするほうではないのですが、こうして写真で見るとやはり電柱の無い路地はいいですね。
新興住宅街で育った子達は、日本風のものを知らなくて、日本の歴史や文化を教える時に、ピンと来ないものがあるそうです。すると先生達はテレビで時代劇を見るように勧めるのだとか。
こういう街並みの中で育つのも、うらやましいですね。
普段そんなに気にするほうではないのですが、こうして写真で見るとやはり電柱の無い路地はいいですね。
新興住宅街で育った子達は、日本風のものを知らなくて、日本の歴史や文化を教える時に、ピンと来ないものがあるそうです。すると先生達はテレビで時代劇を見るように勧めるのだとか。
こういう街並みの中で育つのも、うらやましいですね。
Posted by ゲスト at 2006年05月16日 13:55
臼杵は何かつながりがあるのでしょうか?
愛媛の温泉に行ったという伝承があったと思いますが、大分でも太子信仰が盛んだったのでしょうか?
愛媛の温泉に行ったという伝承があったと思いますが、大分でも太子信仰が盛んだったのでしょうか?
Posted by さるのすけ at 2006年05月16日 22:08
>Laylaさん、こんばんは。
そうですね。この地区には電柱あまり見かけませんね。うちの近所には少しありますけど。
やはり歴史保存地区ということで、九州電力も協力しているのかもしれません。
そうですね。この地区には電柱あまり見かけませんね。うちの近所には少しありますけど。
やはり歴史保存地区ということで、九州電力も協力しているのかもしれません。
Posted by Kiyo at 2006年05月16日 22:41
>さるのすけさん、こんばんは。
臼杵と聖徳太子の関係はあまり聞きません。この三重塔を建てるときに、高橋団内は奈良や京都の神社仏閣を参考にし、検討したそうです。ただそのくらいのようです。
臼杵と聖徳太子の関係はあまり聞きません。この三重塔を建てるときに、高橋団内は奈良や京都の神社仏閣を参考にし、検討したそうです。ただそのくらいのようです。
Posted by Kiyo at 2006年05月16日 22:43
kiyoさんは大分の出身でいらっしゃるんですね。私は高校まで福岡に住んでいました。なので親しみを感じます。昨年臼杵の石仏を見に行った時、仁王座歴史の道を歩いてきました。のどかでとってもいい町ですよね。聖徳太子のお寺お昼に黄飯を頂いたお店でクチナシの実を買ってきて自分でも炊いてみました。サフランライスみたいですよね。
今度竹田にも行ってみたいと思っています。
http://blog.livedoor.jp/kimu_sun/archives/cat_10024477.html?p=2
今度竹田にも行ってみたいと思っています。
http://blog.livedoor.jp/kimu_sun/archives/cat_10024477.html?p=2
Posted by キム at 2008年02月24日 19:41
>キムさん、こんばんは。
ハイ、私は臼杵の出身です。この歴史地区とかは子供の頃遊びまわっていたところです。
黄飯も子供の頃食べていたのは、ダイコンを小さく切って醤油で味付けてご飯に混ぜていたのを言っていたような気がします。くちなしの実で色を付けたご飯を知ったのは大人になってからでした。
竹田は城跡があるので、桜の頃がいいですね。それと紅葉の頃かなあ。
渡ると滝廉太郎の作曲した曲が流れる橋だったかトンネルだったかがあるはずですので、ネットでよく調べてからお訪ねくださいね。
ハイ、私は臼杵の出身です。この歴史地区とかは子供の頃遊びまわっていたところです。
黄飯も子供の頃食べていたのは、ダイコンを小さく切って醤油で味付けてご飯に混ぜていたのを言っていたような気がします。くちなしの実で色を付けたご飯を知ったのは大人になってからでした。
竹田は城跡があるので、桜の頃がいいですね。それと紅葉の頃かなあ。
渡ると滝廉太郎の作曲した曲が流れる橋だったかトンネルだったかがあるはずですので、ネットでよく調べてからお訪ねくださいね。
Posted by Kiyo at 2008年02月24日 20:11